
運送業

複雑な運送業の手続きを
スピーディーに解決します
運送業を始めるには、厳格な法令に基づいた許可申請が必要です。
しかし、要件は複雑で専門知識が求められるため、個人での対応は大きな負担となりがちです。
当事務所では、運送業の新規許可から更新、変更手続きまで、経験豊富な行政書士が迅速・確実にサポートいたします。
運送業を始めるには、
厳格な法令に基づいた許可申請が必要です。
しかし、要件は複雑で専門知識が求められる
ため、個人での対応は大きな負担と
なりがちです。
当事務所では、運送業の新規許可から更新、
変更手続きまで、経験豊富な行政書士が迅速・
確実にサポートいたします。
こんなお悩みはありませんか?

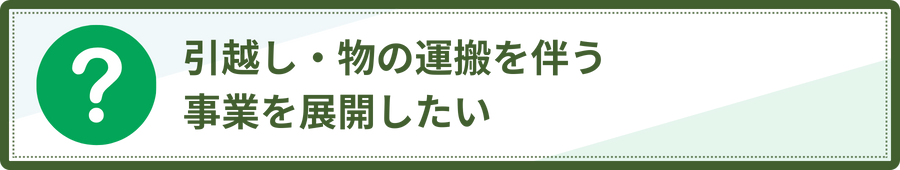
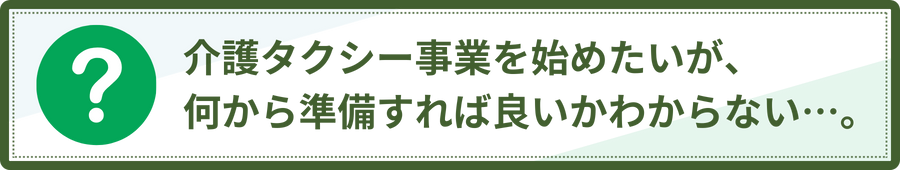
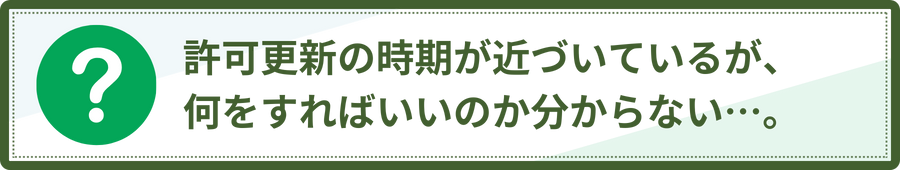
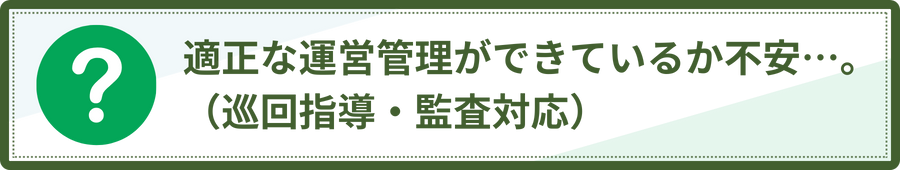
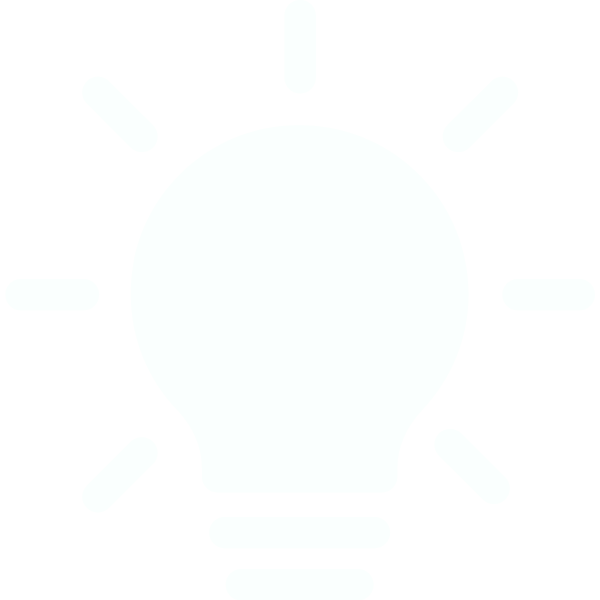
業務案内

一般(軽)貨物自動車運送事業

・引越・物流・運搬事業等の開業
・運送業許可申請書の作成・提出代行
・事業計画書・資金計画の作成支援
・施設棟の要件確認と整備アドバイス

一般旅客自動車運送事業

・タクシー・バス・福祉タクシー等の開業
・許可申請書作成・提出代行
・車両の設備要件チェック
・運行計画書の作成支援

自家用有償旅客運送

・日本版ライドシェア
・道路運送法に基づく登録
・自家用車による有償運送
・許可、運賃認可申請書の作成

一般(軽)貨物自動車運送事業
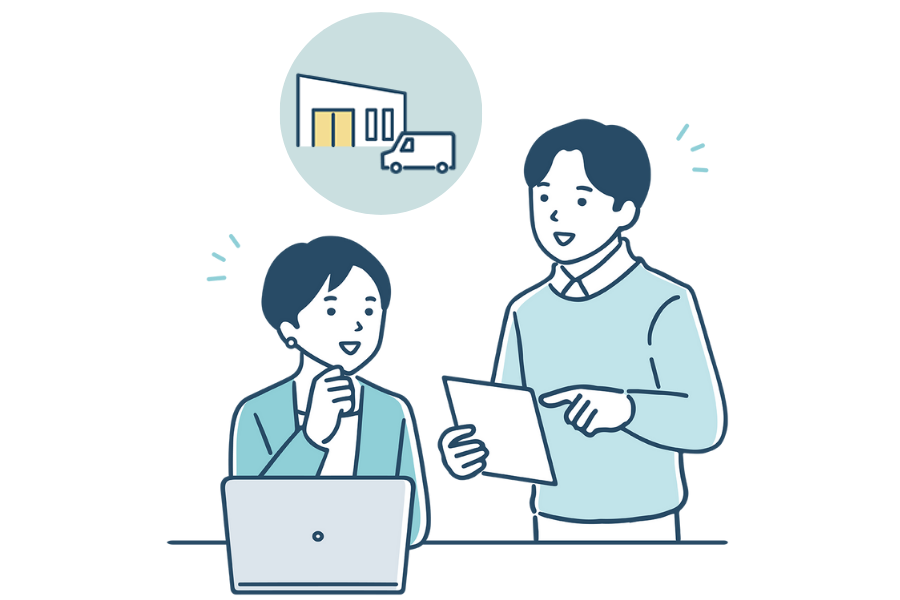
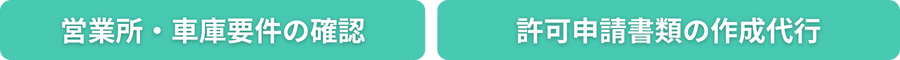



インターネット通販や物流ニーズの拡大により、軽貨物運送事業はますます需要が高まっています。事業を始めるには、運輸局への許可申請や営業所・車庫の要件整備、運行管理者や整備管理者の配置基準など、細かな基準をクリアする必要があります。当事務所では、許可申請書類の作成から要件確認、開業後の法令遵守に関するアドバイスまで、一貫してサポートいたします。
インターネット通販や物流ニーズの拡大に
より、軽貨物運送事業はますます需要が
高まっています。事業を始めるには、運輸局
への許可申請や営業所・車庫の要件整備、
運行管理者や整備管理者の配置基準など、
細かな基準をクリアする必要があります。
当事務所では、
許可申請書類の作成から要件確認、
開業後の法令遵守に関するアドバイスまで、
一貫してサポートいたします。
ご相談一例


一般旅客自動車運送事業
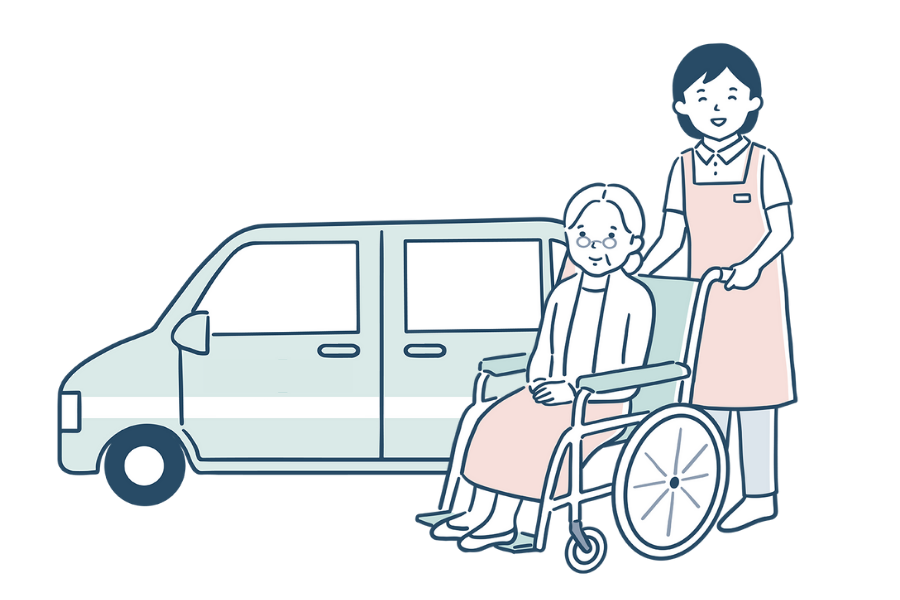




タクシー・バス・介護タクシーなど、人を安全に運ぶ事業を始めるには、厳格な許可要件が求められます。営業区域、運行計画、車両の設備基準、運転者の資格など、多岐にわたる条件を整える必要があります。当事務所では、許可取得に向けた事前準備のご相談から、必要書類の作成・提出、運輸局との折衝までをトータルでお手伝いします。地域の移動ニーズに応える事業立ち上げをしっかり支援いたします。
タクシー・バス・介護タクシー等、人を安全
に運ぶ事業を始めるには、厳格な許可要件が
求められます。営業区域、運行計画、車両の
設備基準、運転者の資格など、多岐にわたる
条件を整える必要があります。当事務所では、
許可取得に向けた事前準備のご相談から、
必要書類の作成・提出、運輸局との折衝まで
をトータルでお手伝いします。
地域の移動ニーズに応える事業立ち上げを
しっかり支援いたします。
ご相談一例


自家用有償旅客運送事業
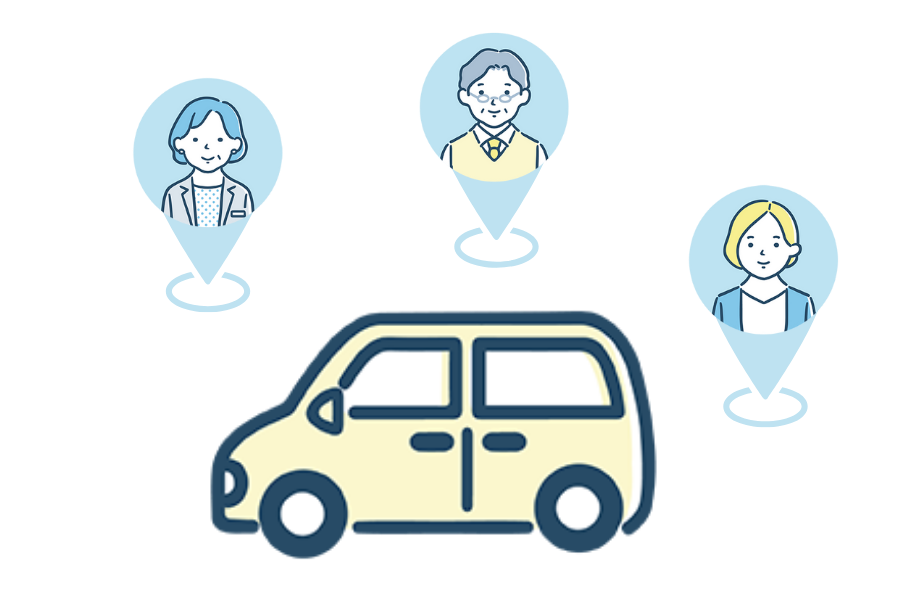
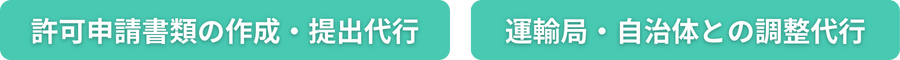
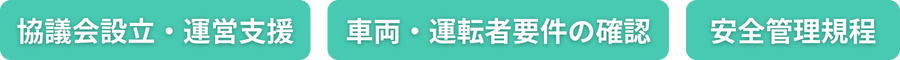


少子高齢化や過疎化が進む中で、地域住民の移動手段を確保するために導入されたのが 「自家用有償旅客運送(日本版ライドシェア)」制度 です。公共交通機関だけでは十分にカバーできない移動ニーズに応える仕組みとして、自治体やNPO、事業者が自家用車を活用し、有償で旅客輸送を行うことが認められています。「地域の足を守りたい」「新しいライドシェア事業に挑戦したい」――そんな思いに当事務所は全力でサポートいたします。
少子高齢化や過疎化が進む中で、地域住民の
移動手段を確保するために導入されたのが
「自家用有償旅客運送(日本版ライドシェア)」制度 です。公共交通機関だけでは
十分にカバーできない移動ニーズに応える
仕組みとして、自治体やNPO、事業者が
自家用車を活用し、有償で旅客輸送を行う
ことが認められています。
「地域の足を守りたい」
「新しいライドシェア事業に挑戦したい」
――
そんな思いに当事務所は全力で
サポートいたします。
ご相談一例




